【建設業専門】未払い残業代を無料で診断
人手不足の建設業で、採用・定着率アップを進めていくには、従業員が働きやすい環境を整備することが必要です。労働環境の整備の第一歩として、まずは、未払い賃金が発生する環境になってないか無料診断してみませんか?診断は5つの質問にご回答いただくだけです。
採用・定着率アップをするには
建設業界の人手不足は年々深刻になってきています。
人を採用したくても、応募がない。採用できても定着しない。すでに、仕事はあっても人手不足で受注できないという事態も起きています。
建設会社にとって、人の採用と定着率アップは、克服しなくてはいけない課題といえます。
人を採用したくても、応募がない。採用できても定着しない。すでに、仕事はあっても人手不足で受注できないという事態も起きています。
建設会社にとって、人の採用と定着率アップは、克服しなくてはいけない課題といえます。
建設業の若手が離職する原因
建設業でなぜ採用・定着率アップが進まないのか? その原因を知る大きなヒントがあります。
国土交通省が、離職した若手技術者へ、何が理由で会社を離職したのかアンケートを行いました。
その結果は、
1位:雇用が不安定であること 2位:遠方の作業が多いこと 3位:休みが取りづらいこと
が、離職原因のトップ3として挙げられています。
この原因を裏返していえば、次のように解釈できます。
・雇用が不安定である→日給月給で毎月一定額の給与を受け取れない→賃金制度に不安がある。
・遠方の作業が多い→会社に長時間拘束され自由な時間が少ない→長時間労働に不満がある。
・休みが取りづらい→人が少なく業務が多忙で、休みを取りづらい雰囲気がある→休日が少なく、有休制度も機能してない。
逆にいえば、これら原因を改善していけば、採用も定着率も上がっていくといえるでしょう。
つまり、従業員が働きやすい環境を整えること、労働環境の整備が必要ということです。
国土交通省が、離職した若手技術者へ、何が理由で会社を離職したのかアンケートを行いました。
その結果は、
1位:雇用が不安定であること 2位:遠方の作業が多いこと 3位:休みが取りづらいこと
が、離職原因のトップ3として挙げられています。
この原因を裏返していえば、次のように解釈できます。
・雇用が不安定である→日給月給で毎月一定額の給与を受け取れない→賃金制度に不安がある。
・遠方の作業が多い→会社に長時間拘束され自由な時間が少ない→長時間労働に不満がある。
・休みが取りづらい→人が少なく業務が多忙で、休みを取りづらい雰囲気がある→休日が少なく、有休制度も機能してない。
逆にいえば、これら原因を改善していけば、採用も定着率も上がっていくといえるでしょう。
つまり、従業員が働きやすい環境を整えること、労働環境の整備が必要ということです。
労働環境の整備=就業規則の整備
労働環境の整備を具体的にいうと、就業規則を整備することになります。
就業規則とは、その会社の、賃金などの労働条件や労働時間、休日に関すること、服務規律についてなどの決まり事を定めたルールブックになります。
賃金、労働時間、休日に関して見直した場合は、就業規則も変更しなくてはならず、労働環境を従業員が働きやすいように改善した場合は、おのずとその内容が就業規則に反映されます。
※常時10人以上の従業員を雇っている場合は、就業規則の作成、労働基準監督署への届出が義務となります。
自社の労働環境を言語化したもの、それが就業規則です。
したがって、労働環境の整備とは就業規則の整備とイコールになります。
就業規則とは、その会社の、賃金などの労働条件や労働時間、休日に関すること、服務規律についてなどの決まり事を定めたルールブックになります。
賃金、労働時間、休日に関して見直した場合は、就業規則も変更しなくてはならず、労働環境を従業員が働きやすいように改善した場合は、おのずとその内容が就業規則に反映されます。
※常時10人以上の従業員を雇っている場合は、就業規則の作成、労働基準監督署への届出が義務となります。
自社の労働環境を言語化したもの、それが就業規則です。
したがって、労働環境の整備とは就業規則の整備とイコールになります。
未払い賃金の発生
従業員の採用・定着率アップのためには、就業規則を見直すことは必須ですが、就業規則を作りっぱなしで未整備のままだと大きなリスクを抱えることになります。
たとえば、労働時間の定義を明確にしておかないと、未払い残業代が発生することになります。
未払い賃金の時効は2年から3年に延長され、今後の消滅期間は5年になるとされていて、 辞めた従業員から、数年後ある日突然請求されるという事態も起こります。
ちなみに、残業時間については、従業員がメンタルや病気・ケガをしていなくても、残業時間の是正を放置していとして、会社が安全配慮義務違反を命じられた判決も出ています。
残業リスクは、経営者にとってますます大きくなっているといえます。
たとえば、労働時間の定義を明確にしておかないと、未払い残業代が発生することになります。
未払い賃金の時効は2年から3年に延長され、今後の消滅期間は5年になるとされていて、 辞めた従業員から、数年後ある日突然請求されるという事態も起こります。
ちなみに、残業時間については、従業員がメンタルや病気・ケガをしていなくても、残業時間の是正を放置していとして、会社が安全配慮義務違反を命じられた判決も出ています。
残業リスクは、経営者にとってますます大きくなっているといえます。
就業規則を未整備のままにするリスク
それ以外にも、就業規則を整備しないままでいると
・問題を起こした従業員を懲戒処分にできない
・問題社員を解雇できない
・予定していなかった非正規社員の退職金の支払いが発生する
・残業が長時間化すると労働基準監督署の指導が入る
・パワハラ・セクハラを抑制できなくなる
・残業が原因で、従業員がメンタル・病気・ケガを負うと安全配慮義務を問われる
・不平や不満で職場の雰囲気が悪くなり、離職する従業員が増える
などが起こります。
そしてその行き着く先には、罰金や損害賠償・慰謝料の請求が待っています。
現代は、コンプライアンスの遵守について、厳しい目を向けられています。
もし、コンプラ違反が衆知されることになれば、従業員の離職を招き、求人を出しても応募がないどころか、公共・民間の工事の入札に参加できないといったことまで影響してきます。
労働環境を整備し、コンプライアンスを遵守することも、今の時代は必須といえます。
・問題を起こした従業員を懲戒処分にできない
・問題社員を解雇できない
・予定していなかった非正規社員の退職金の支払いが発生する
・残業が長時間化すると労働基準監督署の指導が入る
・パワハラ・セクハラを抑制できなくなる
・残業が原因で、従業員がメンタル・病気・ケガを負うと安全配慮義務を問われる
・不平や不満で職場の雰囲気が悪くなり、離職する従業員が増える
などが起こります。
そしてその行き着く先には、罰金や損害賠償・慰謝料の請求が待っています。
現代は、コンプライアンスの遵守について、厳しい目を向けられています。
もし、コンプラ違反が衆知されることになれば、従業員の離職を招き、求人を出しても応募がないどころか、公共・民間の工事の入札に参加できないといったことまで影響してきます。
労働環境を整備し、コンプライアンスを遵守することも、今の時代は必須といえます。
まずは無料診断へお申込みください
いかがでしょう?
賢明な社長・人事担当者であれば、労働環境の整備の重要性をご理解いただけたと思います。
とくに、未払い残業代が発生する労働環境かどうかは要チェックです。
働いた時間が正当にカウントされないとなると、労働基準法違反に問われることはもちろん、採用や定着率アップに悪影響を及ぼします(請求されれば支払いも発生します)。
そこで、まずは労働環境の整備の一環として、未払い賃金が発生する環境かどうか、無料診断を受けてみませんか?
診断は、アンケートフォームより、5つの質問に「はい・いいえ」にチェックを入れるだけで完了です。
そのご回答をもとに、未払い残業代が発生する状態になってないか、無料で診断いたします。
賢明な社長・人事担当者であれば、労働環境の整備の重要性をご理解いただけたと思います。
とくに、未払い残業代が発生する労働環境かどうかは要チェックです。
働いた時間が正当にカウントされないとなると、労働基準法違反に問われることはもちろん、採用や定着率アップに悪影響を及ぼします(請求されれば支払いも発生します)。
そこで、まずは労働環境の整備の一環として、未払い賃金が発生する環境かどうか、無料診断を受けてみませんか?
診断は、アンケートフォームより、5つの質問に「はい・いいえ」にチェックを入れるだけで完了です。
そのご回答をもとに、未払い残業代が発生する状態になってないか、無料で診断いたします。
大畑 寛泰プロフィール

はじめまして。ファイナンシャル・プランナー(CFP:国際ライセンス)の大畑 寛泰(おおはた ひろやす)と申します。
銀行員でも税理士でも金融マンでもない網羅的な視点でお金の問題解する「社長専門のお金のエキスパート」です。
1972年、鳥取県生まれ。工業高校卒、アルバイトを含め10種類以上の就転職を繰り返す。金融機関への就職も実務経験もなく、ファイナンシャル・プランナー(国際ライセンスCFP)資格を取得し、社長専門のお金のアドバイザーとして活動するFP。
実務経験のなさをカバーする、法人財務、法人・個人のタックスプラン、社会保険料適正化、銀行融資、金融商品まで網羅する知識で、銀行員でも税理士でも金融マンでもない総合的な視点で、社長の抱えるお金の悩みを解決。
法人と個人を一体化した、社長のお金を「増やす」「運用する」「移転する」「守る」財務コンサルティングを展開中。
<一言コメント>
社長のお金の悩みは多岐にわたります。それを社長一人だけで解決しようとするのには無理があります。だからこそ、お金のアドバイザーが必要です。ご家族のこと、会社のこと、従業員のこと、取引先のこと、本当に周りの人の幸せを想う社長ほどお金の悩みは深刻になります。そんなプレッシャーに耐えながら人生に真摯に向き合う社長のお役に立ちたいとわたしは思っております。
著書:FPが教える社長のお金を増やして守る節税術
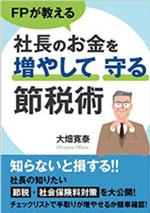
簡単無料診断の流れ
1.アンケートフォームから送信
アンケートフォームから質問にご回答いただき、そのまま送信してくださいませ。
2.3営業日以内に診断内容を返信
アンケートフォームからいただいた御社の回答を基に、未払い残業代が発生する労働環境になってないか診断いたします。診断内容は3営業日以内に返信いたします。
3.個別相談のご案内
もっと詳しく就業規則の内容についてご相談いただきたい場合は、30分無料の個別相談をご案内いたします。
無料診断へのお申込みはこちらから
まずは、アンケートにお答えになって、無料診断へお申込みくださいませ。